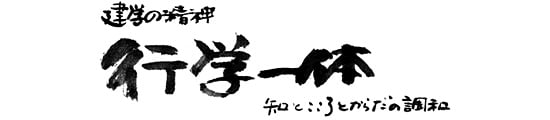

650年前、ある一人の僧がこの地を訪れ、
村人と共に牛を追い、草を刈り、
人々の心に明かりを灯した。
その禅的精神を正眼短大はあかあかと灯しつづけます。

開学者・梶浦逸外老師は、戦後の荒廃した社会の中で、「開山大師がもし今日おられたなら、何を求められるだろうか」と自問し、「仏教や禅の教えを広める場をつくり、学生を教え導くこと」が必要と考えました。
そして「国際社会に裨益(ひえき:役に立つこと)する優秀な人材を育成すべく行学一体の禅的教育による人づくりをめざし、名実ともに奉仕的精神をもって不言実行する人材を送りだす教育機関であることです。」と語られました。
窮而変変而通 窮して変じ、変じて通じる
世の中は常なく、また困難が世の常の姿であり、「楽は苦の種、苦は楽の種」で、いかなる道も道一筋に真剣に努力していると、必ず鉄の壁に突き当たって動きもにじりもならなくなるものである。
窮而変変而通 窮して変じ、変じて通じる
世の中は常なく、また困難が世の常の姿であり、「楽は苦の種、苦は楽の種」で、いかなる道も道一筋に真剣に努力していると、必ず鉄の壁に突き当たって動きもにじりもならなくなるものである。
因が果となり果が因となり、因果は間断なく巡り合って来るので、その因果の道理を常に弁(わきま)えておれば、窮した時には「しめた!」と思って真剣に努力さえしておれば、やがて窮して変じて通ずるものである。それを繰り返して実行してゆくことが、即ち禅の正念相続であり、雲門の「日々是好日」となるのである。
正眼短期大学の学生諸君。“艱難(かんなん)汝(なんじ)を珠(たま)にす”とある通り、自己を磨くために求めて艱難に生きる覚悟で進んでもらいたい。
梶浦逸外老師の「禅心」より

